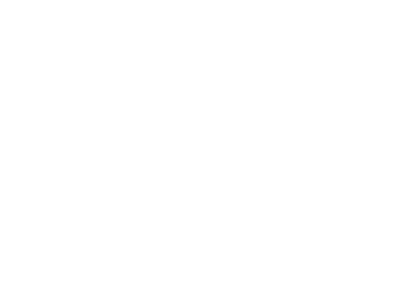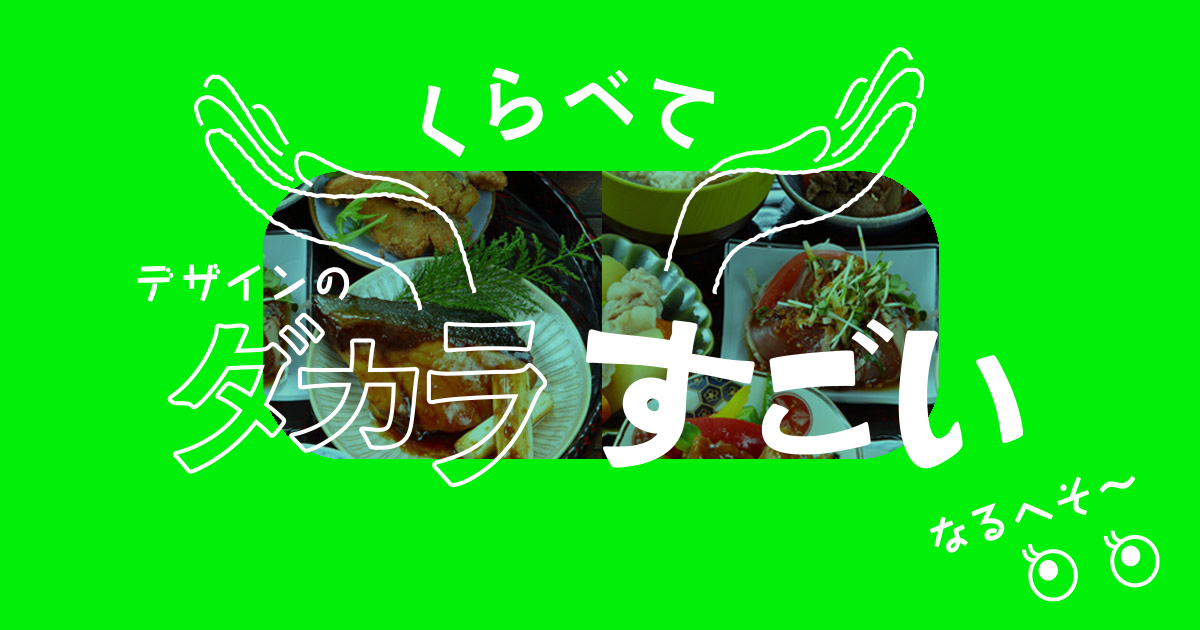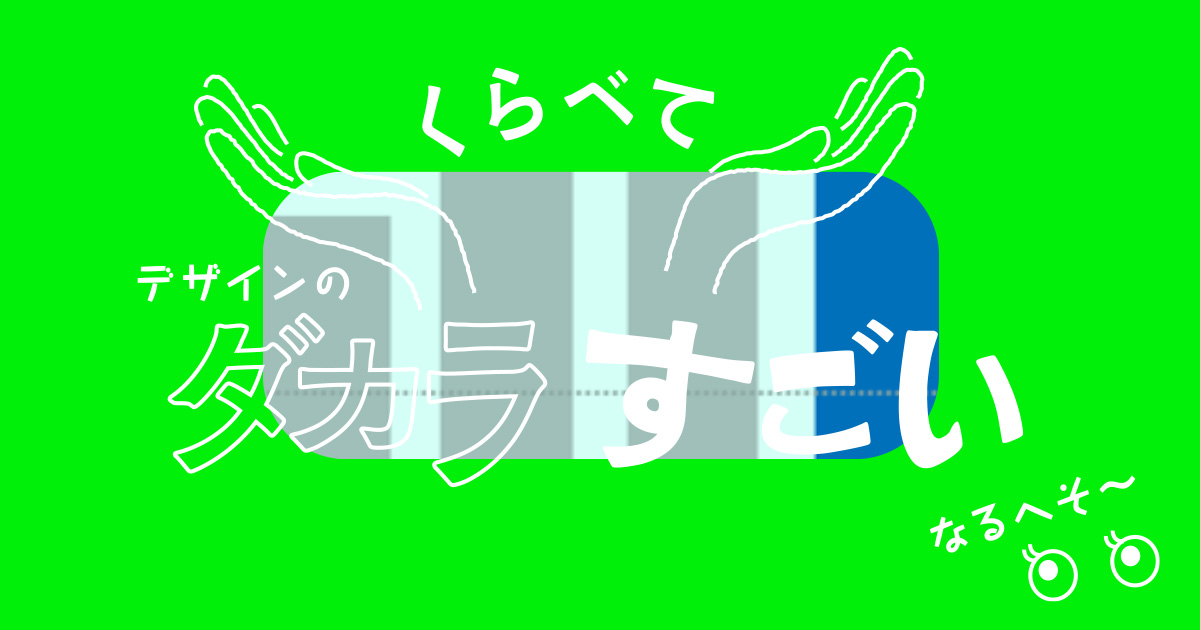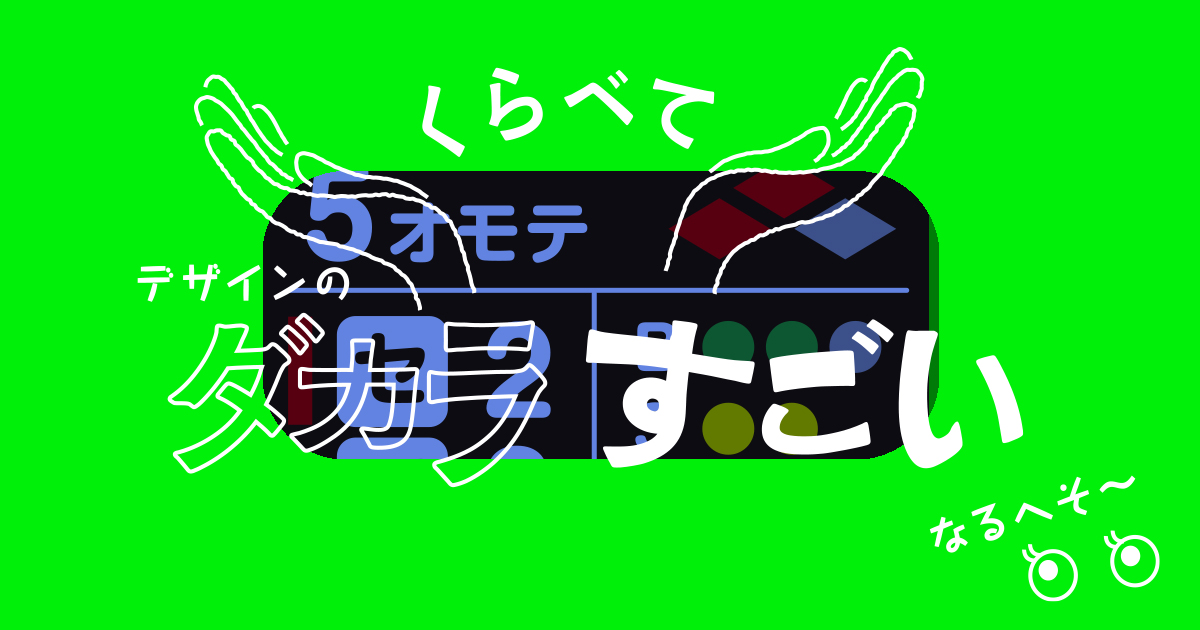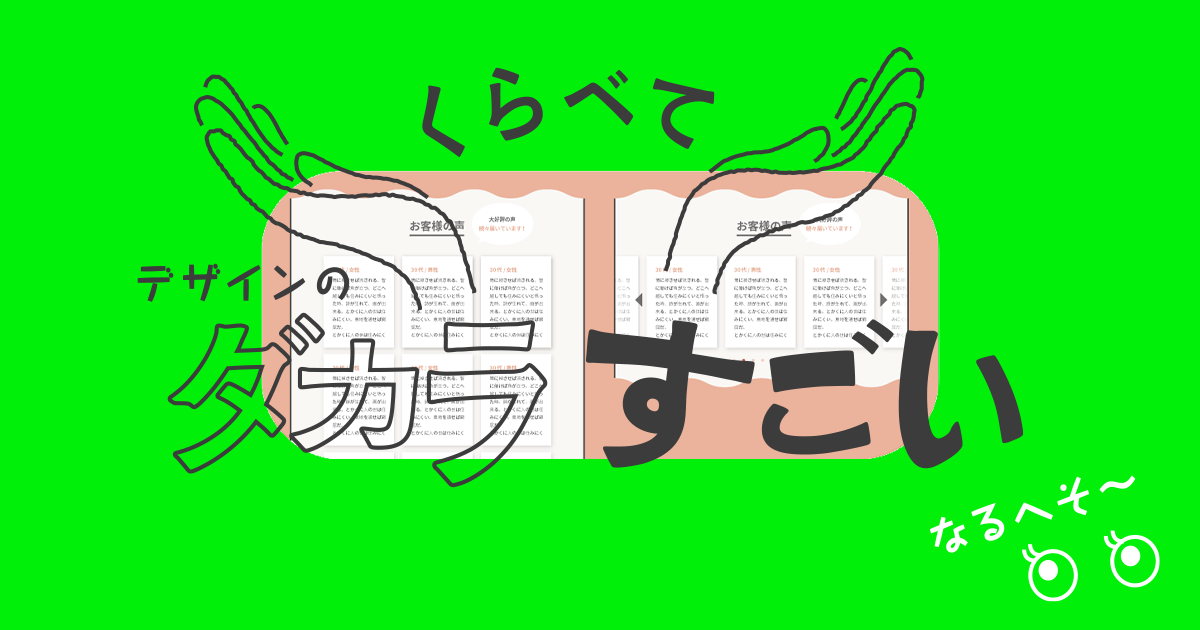「新商品です。写真お願いします」「この◯◯、おいしそうに撮ってください」
これ、実際によくいただくご依頼です。
どんな商品なんだろう、特長は何か。
何に使うのだろう、どこで、どんなサイズで展開するつもりか。
印刷?それともwebやSNS用?動画?などなど。
制作物によっても撮り方やデータの仕上げ方は変わるのですが、
どんな人に届けたいのか、届けた先にどんな気持ちになってもらいたいのか、
そもそも「おいしそう」ってなんだろう・・・
色んなことに考えを巡らせて与件を整理し、必要な情報を集めて想像と創造を膨らませます。
写真の撮り方(手法)だけで言えば、
例えば、盛り付けるお皿によっても、違って見えたり。
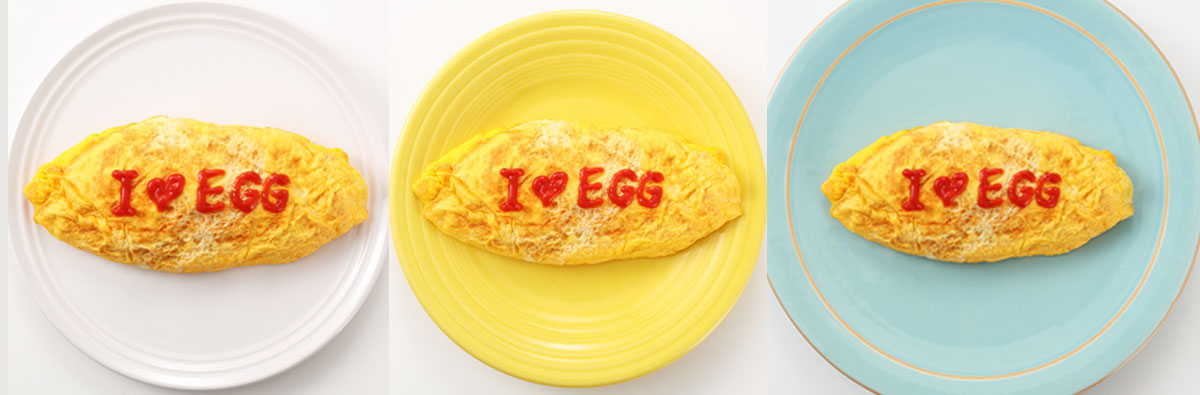
光(照明)によっても印象が変わったり。

角度(アングル)によっても。
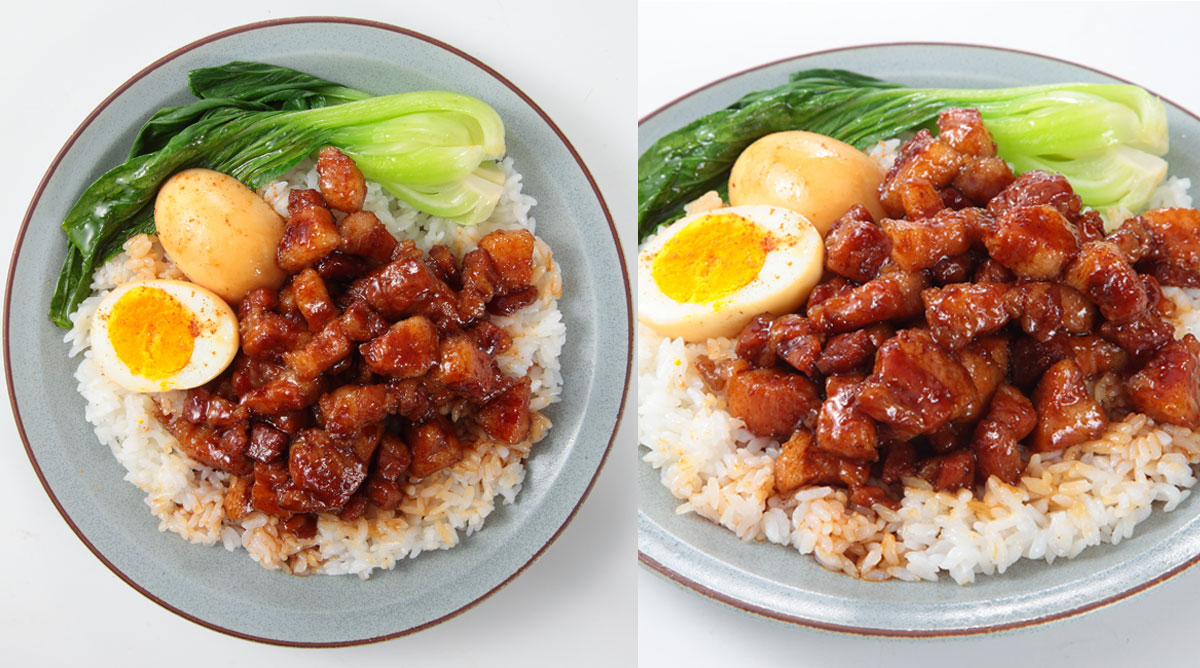

真上からお皿全体を写す「真俯瞰」は、デザイン性が出しやすい反面
やや立体感がなくなる場合もあります。
小さいサイズの制作物には、写真がアップにしにくくより小さくなる分、不向きなことも。
被写体の高さが伝わらないケースもあります。

照明の明るい暗いもそうですが、「熱量」も大切なおいしさの要素です。
例えば「温かさ」の場合、色温度(赤み、彩度)や
湯気、沸騰した際の気泡(グツグツ)具合など。



ピントの合わせ方でも印象の違いが。

「おいしそうに撮ってほしい」
そんな始まりから、課題の本質を捉え、目指すべき方向を企画に定め、
色んな違い、良し悪しを理解した上で、より魅力的になる手法を取捨選択し、デザインする。
そこに視覚化・体験化して伝える仕事の醍醐味がある…と思うわけですが、
「おいしさ」という抽象的なものを一旦「言語化」して、「見える化」する。
そういう視点で見れば、様々な便利が進んでも、
例えば生成AIを活用する人間が、そもそも違いを認識できるか、違いを言語化できるか
という点は、とても重要に思えてきます。
ここでは「食べ物」「撮り方」の一部を例にしましたが、
見たり、触れたり、味わったり、セオリーや背景を学んだり、
生産者や、実際に届けたい相手の声を聞いたり・・・
AI同様に人も、様々な実体験や他者の声を通して、データを蓄積しながら
都度整理して、学び続けなければ…ですね。
マーケティングの本質も、そこにあるように思います。
さて、それでは質問です。
これの違いは何でしょう?

答えは、あなたが感じたこと。だと思います。
だから難しい。だから面白い。のかもしれませんね。
Creative Director 山川未紗
バロック【大阪オフィス】リテールコンサルティング部